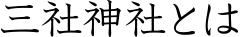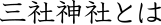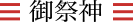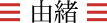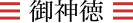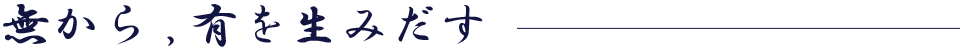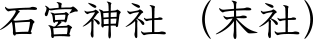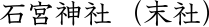大日孁貴命(天照皇大御神)
(オオヒルメムチノミコト)
日本神話に登場する神。
皇室の祖神様で、別名「オホヒルメノムチ」といい「オホ」は尊称「ムチ」は「高貴な者」「ヒルメ」は「日の女神」を表します。
誉田別命(八幡神)
(ホムタワケノミコト)
応神天皇(おうじんてんのう、仲哀 天皇9年12月14日ー応神天皇41年2月15日)の別名誉田別尊の由来は天皇が生まれた時、その腕の肉が弓具の鞆(ほむた)のように盛り上がっていた事にあり、ほむたに譽田をあてたものだといい、また母の神功皇后の胎内にあったときから皇位に就く宿命にあり、「胎中天皇」とも称されました。
武甕槌命(鹿島ノ神)
(タケミカツチノミコト)
火神軻遇突智(カグツチ)の首を切り落とした際、実束剣「天之尾羽張(アメノオハバリ)」の根元についた血が岩に飛散して生まれた三神の一柱神で勝負事にまつわる「武徳の神」とされています。